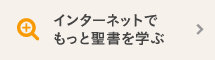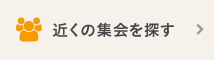レシピ18 「落し所」の法則

広辞苑で「落し所」を調べると、こうなっています。
「決着を付けるために最適な場面。用例。『落し所を探る』、『落し所を心得た人』」
最近は、親や友人を殺傷する青少犯罪が増えています。その理由として、「昔の子は実際に喧嘩をしながら、どこまでできるかを学んだものだが、最近は手加減の分からない子が増えてきたのだ」と主張する人もいます。確かにそういう面もあるでしょう。つまり、喧嘩の落し所が分からない時代になっているとも言えるのです。
喧嘩だけでなく、人間関係においても、裁判においても、ビジネスにおいても、落し所を心得ておくことは極めて重要なことです。
自己評価の落し所
他人から批判されたことのない人は、いないはずです。聖書には、
「軽率なひと言が剣のように刺すこともある。知恵ある人の舌は癒す」
という言葉がありますが、確かに私たちの人生には、言葉が剣のように心に突き刺さることがあります。
批判の言葉を浴びた場合、普通二つの反応が考えられます。一つは、その批判によって打ちひしがれ、立ち上がれないほど落ち込むというものです。当を得た発言であればあるほど、痛みも強烈です。もう一つの反応は、心に鎧をまとって、批判の言葉をはね返すというものです。鎧をまとえばまとうほど、その人は感受性をなくし、友人をなくしていくことでしょう。
どのような局面でも言えることですが、極端な反応は、決してよい結果を生みません。大事なことは、バランスを保った反応をすることです。それができる人は、「落し所を心得た人」です。
バイブルの中の『伝道者の書』は、こう助言しています。
「あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない」
つまり、人間には分からないことがたくさんあるのだから、神のように振る舞ってはならないということです。
また、こういう教えもあります。
「高ぶりが来れば、恥もまた来る。知恵はへりくだる者とともにある」
最高の反応は、批判の言葉が当たっているなら直ちに悔い改め、それまでよりもさらに知恵ある者となって立ち上がることです。
批判の言葉が当たっていない場合は、相手の状況を思いやることです。この点に関して、米国のクレイグ・グロッシェルという牧師は、『牧師の告白』という本の中で、次のような体験談を紹介しています。
「傷ついた人は、他人を傷つけるものである。傷ついた人は、自分のことを嫌っており、他人を批判することで何とか自分を正当化しようとしているのだ。もしそのような人から批判の矢を浴びせられたなら、『理解』という盾でそれを防げばよい。なぜその人がそういう行動を取るのかを考えることは、理解への第一歩である。
ある日曜日の朝、説教の前に目を閉じて祈っていると、誰かが手紙を私の手に置いていった。封筒には、『親展』と書かれていた。きっと私を励ますためだろうと考え、心が温かくなった。しかし、次の瞬間、私の心は冷え切った。その手紙は、怒りに満ちたある婦人からのもので、その中には、金曜日にオフィスを訪ねたが私がいなかったとの苦情が書かれていた(金曜日は、私の休日である)。
これが起こったのは、講壇に立つ直前であった。私には二つの選択肢があった。その批判を個人攻撃と受け取り、がっかりするか。あるいは、こういう手紙を書かざるを得ない彼女の内面を思いやるか。私は、後者を選んだ。
批判を浴びた時は、その源に何があるかを考えればよい。また、批判する人は傷ついた人である可能性があることに思いを馳せればよい。そして、批判を忘れ、先に進むのだ。さもなければ、自分自身が好ましくない人物に成り下がる危険性がある」
ビジネスの落し所
ビジネスにおいても、落し所があります。毎日が落し所を探る作業の連続であると言っても、過言ではありません。
かつてのセールスマン教育では、物を売るための技法の伝授に強調点が置かれていました。その当時は、「エスキモーにでも冷蔵庫を売れるようなセールスマン」が、優秀なセールスマンであるとされていました。つまり、相手が必要としていなくても、テクニックで売りつけるのがセールスマンの仕事だというのです。しかし、このような考え方は、すでに時代遅れです。永続性のあるビジネスを築くためには、落し所をわきまえる必要があります。それが、「ウイン・ウインの関係」です。つまり、両者がともに勝ち組になれるような関係を模索するということです。
日本では、このような商道徳は昔から存在していました。石田梅岩(江戸時代中期の思想家)は、「実の商人とは、先も立ち、我も立つことを思うなり」という言葉を残しています。
また、近江商人の商売哲学は、「三方よし(買い手よし、売り手よし、世間よし)」というものです。近江商人の商売哲学は、他国での商いを通じて生まれた考え方ですが、今でも通用する普遍的な概念です。
人生の落し所
人生において冒険しようと思うなら、「落し所」をわきまえることが大切です。具体的には、失敗した場合のことを考えて行動するということです。最初に最悪の結果を想定し、その範囲であるなら冒険をしてもいいとの判断が成り立つなら、かなり大胆に行動することができます。
ここ数年、団塊の世代の定年問題が頻繁に論じられています。退職して年金生活に入る人たちは、自己所有の資金を少しでも増やすために、投資の勉強を始めているようです。金融商品のパンフレットには、「年○○%の収益」といったうたい文句が躍っています。しかし、失敗した場合のことを想定しないままで、このようなうたい文句に乗ってはなりません。これから投資しようと考えようとしている人は、失敗した場合の許容範囲(落し所)はどこなのかを熟慮し、生活そのものを脅かすような投資をしてはなりません。
このところ、北欧のハイテク産業は驚くほど発展していますが、このことと社会福祉制度の充実とは無関係ではありません。ベンチャー企業を起こすことには相当なリスクが伴いますが、北欧の人たちは、たとえ失敗しても生活できなくなる不安がないため、果敢に新しいことにチャレンジできます。その結果、ハイテク関係の新発見が続出しているのです。日本は小さな政府を目指していますが、それが貧弱な福祉政策をもたらす結果となるなら、国民は冒険をしなくなるでしょう。日本社会の活力が消えうせることを危惧します。
「死ぬ気になれば、なんでもできる」という言葉があります。確かにそうでしょう。私たちはみな、最後は死にます。それが、最悪の状況を想定するということです。もしその状況が許容範囲だと言えるようになるなら、人生観は180度変わることでしょう。
1999年12月6日号の『USAトゥデイ』誌に、記者のキャシー・ハイナーが次のような一文を寄稿しています。彼女は、ガンで闘病生活を送っていましたが、この頃は死期が近づいていました。
「夜中に目覚めて、ベッドの上に座ったまま、3歳児のように泣くことがあります。長い夜が恐ろしくて仕方がないのです。それとは逆に、心が平安で満たされる時もあります。自分は正しい場所にいる、死後の命はある、と確信しているからです。
一人の友人が最近教えてくれた『たとえ話』が、私にとって慰めになっています。この『たとえ話』は、デイビッド・マーカスという大佐の遺体から見つかったものです。彼は、ユダヤ系アメリカ人で、イスラエル国防軍の設立のために尽力した人です。その『たとえ話』とは、次のようなものです。
(私は今、海岸に立っている。目の前を、白い帆を一杯に張った船が朝風に吹かれて進んでいく。その船は、美と力の極致である。やがて船は、水平線に浮かぶ小さな白いリボンのようになった。すると、そばに立っている人が、『ああ、船がいなくなった』と叫んだ。
いなくなった?一体どこへ行ったのか?私の目から消えただけのことだ。その船の大きさや美しさは、先ほど目の前を通過した時となんの違いもない。誰かが『ああ、船がいなくなった』と叫んだ瞬間、向こう側では、別の誰かが『見えたぞ。船がやって来た』と叫んでいるのだ。死ぬとは、そのようなことなのだ)
この『たとえ話』によって、私は大いに励まされているのです」
死の彼方にある希望を確信したキャシー・ハイナイーは、まさに人生の「落し所」を発見した人と言えます。
この章のポイント
1. 他人から筋の通らない批判を受けた時は、相手のことを思いやれ。
2. ビジネスにおいては「ウイン・ウイン(WIN/WIN) の関係」を追及せよ。
3. 若いうちから「人生の落し所」を探る努力をせよ。