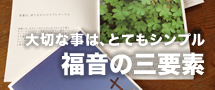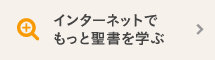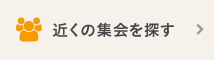2023
01.05
Q.333 患難期前携挙説の根拠は何ですか。
![]()
テキストで読む
Q.質問
Q:友人から、携挙が患難期の前に起こるという根拠は何かと質問されました。分かりやすく答えるためには、どうすればよいですか。
A.回答
A:はじめに
(1)携挙とは、教会(真の信者)が生きたまま天に挙げられることです。
(2)患難期とは、7年間続く苦難の時です。
(3)患難期に入る前に教会が天に挙げられるという説を、患難期前携挙説といいます。私は、その説を採用しています。その理由を、いつものように3つ申し上げます。
1番目に、患難期を預言している黙示録6~18章には、教会への言及がありません。
(1)つまり、患難期においては、地上に教会が存在しないということです。
(2)黙1~3章は患難期前の出来事の預言ですが、そこには教会が存在します。
(3)黙19~22章は患難期後の出来事の預言ですが、そこにも教会が存在します。
2番目に、患難期の目的は不信仰を裁くことですので、教会は患難を通過する必要がありません。
(1)特に、イエスを拒否したユダヤ人の上に厳しい裁きが下ります。
(2)信者は信仰と恵みによって救われていますので、裁かれる必要はありません。
(3)悪魔は、ユダヤ人を抹殺するために彼らを苦しめます。
(4)神は、苦難を通過させることによって、ユダヤ人を救われます。
(5)ユダヤ人の民族的救いは、キリストの再臨の前提条件です。
3番目に、信者が患難期から救われることを約束した聖句がいくつもあります。
(1)1テサ1:9~10 「やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエス」
①ここでの「御怒り」とは、患難期における神の怒りのことです。
②携挙は、信者にとっては希望です。
(2)黙3:10 「全世界に来ようとしている試練の時には、わたしもあなたを守る」
①ここでの「試練と時」とは、患難期のことです。
(3)黙22:20 「しかり、わたしはすぐに来る」
①携挙は、「すぐに起こり得る」状態にあります。
②患難期の中間でも、その後でもありません。
携挙がきょう起こってもいいような備えをしている人は、幸いです。